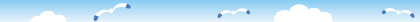
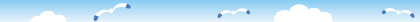

5 ふかざ るも <Hello,Everybody!!楽しい楽しいお昼の時間。エンターテイナー吹風 流雲で〜す!!> 昼食の時間。 放送委員の流雲の陽気な声が、スピーカーから流れ出る。 <皆さん、今日のこの日を待ち望んでいてくれたことでしょう!今日も元気いっぱいでいきましょう!HERE WE GO!!> 週に2回、流雲の順番が回ってくる。 緊張する様子はさらさらなく、達者に動く口。 <明日から、期末テストが始まります!もー、僕どーしようって感じ。でも、そーゆー皆さん!めげちゃいけません。愛があれば何だって乗り切れます!!> スピーカーからの声に、クロスが、なんだそりゃ。と眉をひそめた。 夜司輝たちも、一様に呆れた顔。 <実は僕。志望校受かんないってゆわれてるんです!> 泣くマネをして――、 <でも、志望校には、僕の愛しの人がいるんで、絶対合格します!> 「放送でゆーかフツー……。」 すくむ 灰色の四角い物体を仰ぎ睨んで、竦。 つばき 「椿がいたら、ショックだろうな。」 <皆さんも色んなこと頑張ってくださいね!好きなことがあるって、人間強いですから!!> 何だか、フリートークである。 これでなかなか学校ウケが良く、人気者の流雲。 <そうそう、ここで一つ。ニュースです!> 「何でもありだね……」 隼弓もお弁当片手に、カラ笑い。 <来る8月10日、片瀬江ノ島西海岸にて、僕のジュニアユースサーフィン大会優勝打ち上げやるから、皆来てくれ!!よろしく〜!ほんじゃ、曲いっきま〜す!> 4人全員が一斉に大きな溜息をついた。 「おーい流雲!マジで優勝できなかったら、どーすんだよ!!」 教室に戻ってきた流雲に、机に肩肘をついてクロス。 「えー?んなコト、天と地がひっくりかえってもないってぇ。」 にっこり笑顔。 相変わらずの自信である。 クロスは、あっそ。とだけいって軽く受け流す。 隼弓は、本当に余裕なんだねぇ。と感心。 そして――、 「うわーい!終わったぁ――!!」 甲高いチャイムとともに、大きく伸びをして席を立ったのは、流雲。 教師の叱責もよそに、頭の中は夏休み。 期末試験、全日程終了。 結果はどうあれ、あとは夏休みを待つばかりである。 「んー!気持ちいい、最高!」 放課後、5人はいつものように波乗りを楽しむ。 暑い日差し。 大きく、真っ白な雲がゆっくりと移動している。 片瀬江ノ島西海岸。 紺碧の空に、紺青の海。 純白の雲に、素白の波。 「なーんか。こんな穏やかな波じゃ大会心配だわな。」 腹の下を揺る緩やかな波が通る。 「ほーんと。高い波、ほしいよね。ちょっと怖い気もするけどさ。」 隼弓はかわいく笑って――、 「ほら、映画であったじゃん。でっかい波!パトリック・スウェイジとキアヌ・リーブス。あの。チューブすごかったよなぁ。」 ハート・ブルー。 1991年、K・ビゲロー監督、指導者ジェームズ・キャメロン作の映画。 チューブとは、勢い余った波が前方に崩れ、そこにできる空洞のことだ。 「オーストラリアの伝説のBIG WAVEだよな。」 「そうそう。BIG WAVEっていやー、稲村ジェーン!」 稲村ジェーン。 ミュージシャン、Southern All Stars、桑田圭祐作の映画。 若者たちに大好評で、上映延長された作品である。 稲村ガ崎や江ノ島。 逗子マリーナなどを撮影地としていて、地元の流雲たちには馴染み深い。 「でも。やっぱBIG WAVEは伝説だよなぁ。」 「マスター見たってゆってたじゃん。」 「たまたまだろ。20年に一度なんてありえないって。」 クロスは長い黒髪をかきあげた。 太陽がボードに当たり、輝く。 「来るって、絶対!」 満悦の笑みを漏らす流雲に、これだよ。と、呆れ顔。 「せめて、オフショアの風だったらいんだけどね。」 優しく笑って夜司輝。 オフショアの風とは、陸から海に向かって吹く風のことで、それによって立った波は、簡単には崩れずに先端が白く飛ばされる。 サーファーには絶好の風だ。 「チューブ入ってみたいなぁ。」 流雲は青空を振り仰ぐ。 すばやく方向転換して沖にでた。 そして、パドリング。 波の崩れないところまで出て、ボードの上に座る。 沖を向き、いい波を待った。 自分の波を決め、サーフボードに腹ばいになり、もう一度パドリング。 ゆっくり、流雲の体が波に持ち上げられる。 一番高くなったところで、流雲は膝をつき、両腕でバランスをとりながら、立ち上がった。 テイク・オフ。 流雲のサーフボードが水の青の壁をいっきに下り始めた。 白く、綺麗な航跡が一直線に伸びる。 流雲は波の斜面を下りきったところで、右手を海面につくようにして、ターン。 「おーお。でっけぇスプレー飛ばしやがって。」 スプレーとは、波上でターンをする時に飛ぶ水飛沫のことである。 あとは、そのまま波に体を委ね、ボードに乗っていればいい。 楽々海岸へ向かって、流雲はすべっていった。 「でもさぁ。俺、流雲のライディング好きなんだよねぇー。」 流雲意外は、まだ沖で揺られている4人。 隼弓は口を開く。 「何か、海が好きだぁー!って感じ?流雲らしくてさ。」 「俺も、好きだよ。でも、悔しーからゆってやんない。」 クロスの言葉に、竦も同意して言う。 「あいつなら、マジで優勝できっかもな。」 何だかんだ言っても、流雲のサーフィンテクニックには、一目置いているのだ。 「おーい!かわいいこいるぞー!早くこいよー!!」 浜で、大きく両手を振る流雲。 4人は苦笑して――、 「ばーか!ナンパばっかしてんじゃねー!!」 皆、テイク・オフをして流雲を追いかけ、波を駆け下った――……。 >>次へ <物語のTOPへ> |