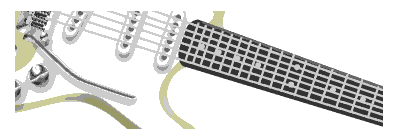三 かいう 「海昊さぁ――んっ。」 三人が去った教室。 つづみ 坡はおもむろに大きな溜息をついて眉間に皺をよせた。 「何でそんなのん気にしてんスかぁー。あいつら、絶対何か企んでるつーのに。」 「のん気……ちゃうけど。せやって何もされてへんゆうに、シカトする必要もあらへんやろ。」 「何かされてからじゃ遅いじゃないスかぁ――!」 坡は海昊の机にうなだれるように倒れ込む。 ささめ でも。と、真剣な顔をするのは細雨。 ヤ 「俺の気のせいでしょうか。あの三人。俺たちは、お前たちがゾクだって知ってても殺れる自信があるんだぞ。って、ゆってるように聞こえました……」 てつき 轍生も同意した。 ささあ 篠吾は両手のひらを天井に向け――、 「でーも、そんな奴らワケないすよ。」 たきぎ 「そりゃ、俺らがいるからへーキだけどよ。薪さんも気をつけてくださいよ。」 坡の言葉に、 「ばーか。俺を誰だと思ってんだよ。」 薪は鼻をならした。 「……やっぱ裏を感じますよね。」 黒紫も細雨に賛同しているようだ。 眉間に皺を寄せた。 数秒の沈黙の後、甲高いチャイムがなったので、 「皆、クラス戻らんと。」 海昊は促した。 六限の終わりのチャイム。 坡は、語尾をさげて、少し不服そうに返事をした。 「心配おおきに。」 そんな坡の気持ちを察して、海昊はにっこり笑ってみせる。 「……っそっりゃあ、海昊さん強いし。あんな奴らに負けるワケないスけどぉ――」 俺らもいることだし。と強調。 上目遣いの坡に海昊は、もう一度礼をいう。 「じゃあ、帰りに。」 少し納得したように、坡をはじめ皆は頭を下げて、教室をでていった。 「……。」 微妙に口をとがらせて、海昊の側に突っ立っているのは、薪。 「……大丈夫やてぇ、薪。」 「べっつに心配なんてしてねぇよっ。ただよ、てめぇーは甘すぎっから……イコールだまされやすいってことなんだよ!」 照れ隠しの薪の言葉。 言い方は乱雑だが、海昊を心配している気持ちが伝わる。 「気をつけます。」 海昊は笑った。 左のエクボがへこむ。 「け。」 薪は海昊を一瞥して、そしてズボンのポケットに両手をつっこみ、自分の教室へ向かった。 その背を見届けて――、 「ふう。」 海昊は声に出して溜息をついた。 窓の外を眺め見る。 K学園は山々に囲まれているので、この季節、緑がとても綺麗だ。 今日は特別に晴れ渡った青の空。 木々とのコントラストが格別だ。 「大阪も晴れなんかいな……」 独り言を呟く。 溜息をもうひとつ吐いた――……。 放課後。 学校から少しはなれた場所で、エンジンのアイドリング音が響き渡る。 良く手入れの行き届いた低音。 坡は、お気に入りの単車、KAWAZAKI EX-4にまたがり、アクセルグリップを軽く回す。 ディープブルーのメタリックカラーにスリムでコンパクトなボディ。 轍生は、黒に黄色のラインの入ったSUZUKI DR800S。 「あ、来た来た。」 坡が顔を上げる。 「お待たせです。」 篠吾は、頭を下げて笑顔でSUZUKI RG 250に鍵を差し込んだ。 小柄な身体にあわせた軽量タイプの単車だ。 黒紫も頭を下げ、KAWASAKI GPX400にまたがる。 海昊も薪も、細雨も皆そろった。 「薪さん、やっぱZEPHYRかっくいースよね。」 きさらぎ 「そーいえば、如樹さんにもらったんすよね。」 坡が薪がまたいだ単車、KAWASAKI ZEPHYRを見ていい、篠吾が付け加えた。 ダークパープルが輝くネイキッド。 「修理にだしてまで譲ってくれてんから、相変わらずな奴や。」 海昊は、HONDA VRX ROADSTARをバックさせる。 ボディーが黒光りしている。 「いらねーっつーからもらってやっただけだよ。」 薪は唇を尖らせ、横浜なんか本当にいくのかよ。と、そっぽを向いた。 きさらぎ みたか 元々は、元BADの特隊、如樹 紊駕の愛車であった、ZEPHYR。 去年の冬の抗争にて壊れた箇所を直し、さらに、薪の単車、SUZUKI GSX750Fは、店に預けていたので、借りる運びが譲ってくれたのだ。 口ではこういっているが、愛車が戻ってきたら返すつもりでいることは皆わかっていた。 あおい 「細雨も滄さんからもらったんだよね。」 見かねて黒紫が細雨に話をふった。 赤のボディーのネイキッド、HONDA CB400FOUR。 細雨は、切り替えしをしながら、 「はい。大切な人からもらったんだから大事にしろって。」 まだ、自由には動かせませんけど。と、かわいく舌をのぞかせた。 それぞれ、エンジンやマフラー、サスペンションなどを思い思いにカスタムしてある七台は、一斉にエンジンを吹かし、横浜へ向かう。 「せやけど、何で山下に知り合いおるん?」 信号待ち。 坡の隣に並んだ海昊。 「その人、元は小町通でライブハウスやってたんスけど、移転?したみたいで。俺らの兄貴分みたいな人っス。な。」 後ろの轍生に視線を送る。 轍生は頷いた。 「そーなん。」 やがて、町並みが変った。 車通りも激しくなり、大通りにでた。 横浜。 「そーだ。あとで中華街いきましょうよ~!」 「あ、俺も行きたい!」 新山下埠頭。 単車をとめて、篠吾が手を挙げた。 細雨も賛同し、 「肉マンやアンマンおいしいですよねぇ!」 黒紫が笑顔でいった。 「OK。じゃ、お礼っつーか。皆の分、俺がおごるよ。」 メットを脱いだ坡は、前髪を手櫛で整える。 赤い髪が頬に触れる。 左頬。 喧嘩の名残が、薄いピンク色に目の下から口近くまで伸びている。 「ほんとですかぁー!」 やった。といわんばかりに喜んだのは篠吾と細雨。 満面の笑み。 黒紫は、申し訳ないという顔を覗かせる。 それぞれの単車を駐輪場に停めた。 新山下出口のすぐそば。 古びた倉庫や建物が人口港沿いに並ぶ。 その倉庫のような建物内にライブハウスやクラブなどが入っている。 若者に人気のスポットとなっている。 どの店もまだ開店前なので、ひっそりとしていた。 とくさ つづし 「木賊 矜さんいますか?」 倉庫の一角。 ベイ シティ 新山下BAY CITY。 坡の言葉に、入り口にいた男は無言で親指を奥のドアに向けた。 「ども。」 頭を下げる坡に皆もついていく。 薄暗い通路の奥。 防音のためだろう、分厚いドア。 坡が開く。 「矜さん。」 「お、来たか。」 細く肩まで伸びた黒髪を後ろで一本に結わいて、丸いサングラスを額の上にかけた華奢な体型の男が手を挙げた。 黒の細身のジーンズにTシャツをラフに着こなしている。 「えっと……」 坡は矜に皆を紹介し、矜を皆に紹介した。 「よろしく。」 些か垂れ気味の瞳が優しそうに笑った。 皆も頭を下げる。 薄暗いフロアでは、たくさんのスタッフが開店準備をしている。 椅子などを動かす者、機材を定位置に運ぶ者。 「ここ自由に使っていいぞ。」 コンサートやDJイベント、披露宴なども開催される、エンターテインメントスペース。 音楽イベントの質は評判高い、BAY CITY。 矜は用意していてくれたスペースを指し示す。 「ありがとうございます。」 「学祭だって?懐かしいなぁ。」 目を細めて、楽器や機材を取り揃えてくれる。 ギター、ベース、ドラム、そしてキーボード。 「そーいえば、何で小町通りの店、閉めちゃった?んスか?」 坡の言葉に、色々あってな。と、曖昧な返事をする矜。 坡と轍生は首を傾げたが、それ以上は追求しなかった。 「お手並み拝見といこうか。」 矜はパイプ椅子に腰掛けて腕組みをした。 坡はエレキギターを肩にかけ、轍生はドラムの後ろに回って腰下ろす。 「久々なんだよなぁ。」 少し照れながら坡はピックをつかみ、素早く調弦してみせ――、 「うわぁ~坡さんかっこいー!!」 「すげぇ~!」 低音から中音、高音。 坡の指が器用に動く。 フロアに響く綺麗な音色に皆が賞賛した。 轍生も負けずにドラムを打ち鳴らす。 「お~、轍生さんもプロいっすねぇ!」 拍手。 二人は照れ笑いを浮かべて目を合わせる。 「ほら、皆もほけっとしてないで。」 坡は皆に指示し、できますかね。と、不安気にいった篠吾たちに、 「大丈夫、先生だってちゃんとついてるし。」 笑顔で、矜に目配せ。 「俺のこと、か?」 大きく頷く坡と轍生に、 「……よーし。やるからには完璧にやるからな。覚悟しとけよ!」 腕をまくり気合を入れる素振りを見せる矜。 皆は一礼し、各々の楽器にとりくんだ。 薪は隅でパイプ椅子に腰に下ろした。 何だかんだいってもついてきた奴である。 「で、肝心のヴォーカルは?」 矜の言葉に坡は海昊に見て、お願いします。と、頭を下げる。 「……せやけど、歌えるかいなぁ。」 「いいね、関西弁。大丈夫、極度の音痴じゃなきゃ。関西の人は比較的歌が巧いって言われてるしね。」 楽天的な矜に、海昊はそうでっか。と、軽く頷いた。 かくして、それぞれの基礎練習が始まった――……。 >>次へ <物語のTOPへ>
|